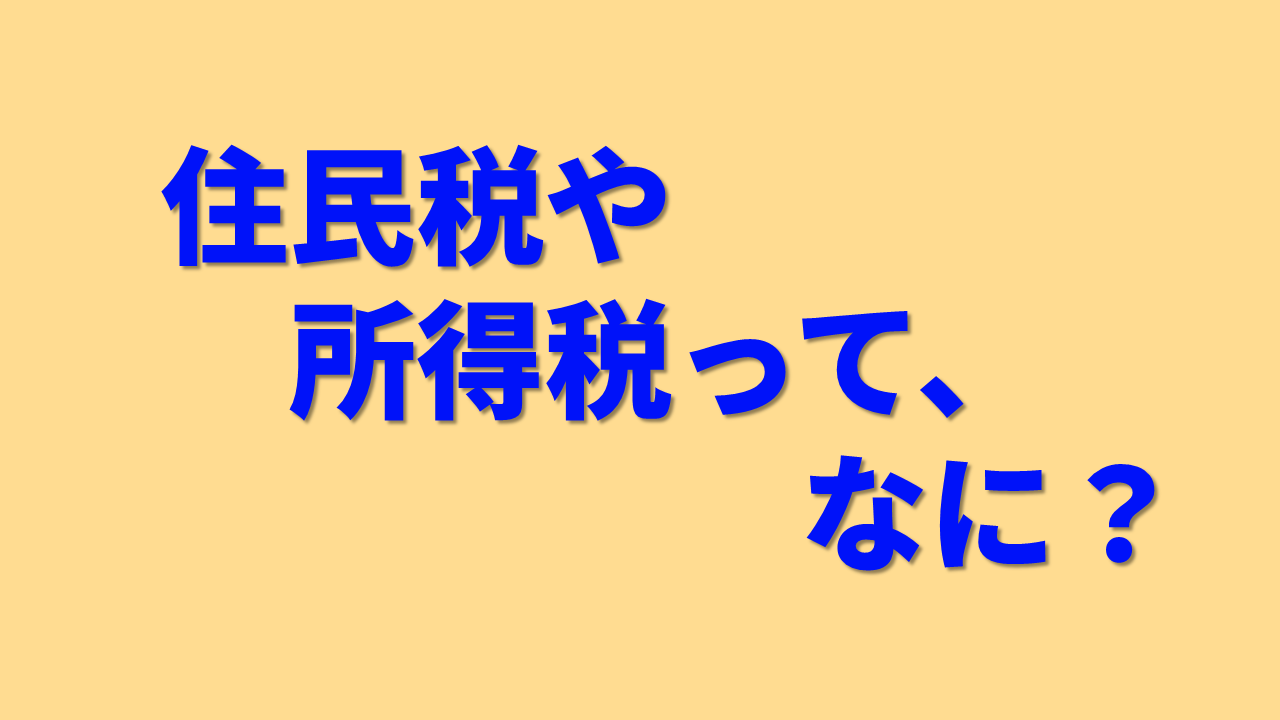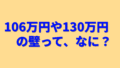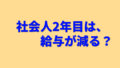父さん、この前、給与の手取りから引かれるものは社会保険と、住民税と所得税って言ってたよね。
その住民税と所得税の金額は、どうやって決まるの?

確かに給与明細に市町村民税や所得税って載ってるけど、計算方法を考えたことはなかったな…。
年金や制度って、なんだろう?
子どもに聞かれて、うまく答えられなかった。
その経験を出発点に、このブログでは、社会保障のしくみを、ひとつずつ、いっしょに見ていきたいと思います。
給与明細を見て「手取りが減ってる?」と思ったことが、あるかもしれません。
その理由のひとつが「住民税」と「所得税」。
どちらも働いて収入を得た人にかかる税金です。
その中身を、少しだけ見てみましょう。
消費税はみんなにかかる
まず、身近なのが消費税。
買い物やサービスを受けるときにかかる税金で、働いているかどうかに関係なく、誰にでもかかります。 2025年現在の税率は10%ですね。
住民税と所得税
住民税は自治体に納める
住民税は、地域の福祉や公共サービスのための財源になります。
自治体ごとに非課税の基準が違いますが、2025年現在は100〜110万円前後が目安です。
住民税がかかる場合、約5,000円(均等割)+一律で所得の10%(所得割)です。
所得税は国に納める
所得税は、収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を差し引いた残りにかかります。
この残りの部分を「課税所得」と呼びます。
所得によって税率は段階的に上がり、少ない人は5%、多い人は最大45%です。
「103万円の壁」とは所得税がかからない目安
これまで、所得税がかからない年収の目安は103万円でした。
でも、2025年から控除額が引き上げられたことで、税金の扶養に入れるラインが123万円に引き上げられました。所得税がかからないラインは160万円です。
「103万円の壁」と言われていたラインが、少し広がったんです。
税金は「全部の収入」にかかるわけじゃない
税金は、収入のすべてにかかるわけではありません。
まず「控除」で一定額が差し引かれ、その残りに税率がかかるんですね。
控除というのは、税金を計算するときに「ここは引いていいよ」となる部分。
これがあると、払う税金が少なくなるんです。
家族の税金にも影響
たとえば、扶養されている人の年収が増えると、世帯主の「扶養控除」が減ることがあります。
その結果、世帯主の税金が数万円以上増えることも。
収入の「壁」は、本人だけでなく家族にも関係してくるんですね。
税金のしくみ、2025年は大きな改正がありました。
最新情報は、国税庁などの公式サイトで確認すると、より理解が深まるかもしれませんね。
[参考]
国税庁「税の種類と分類」