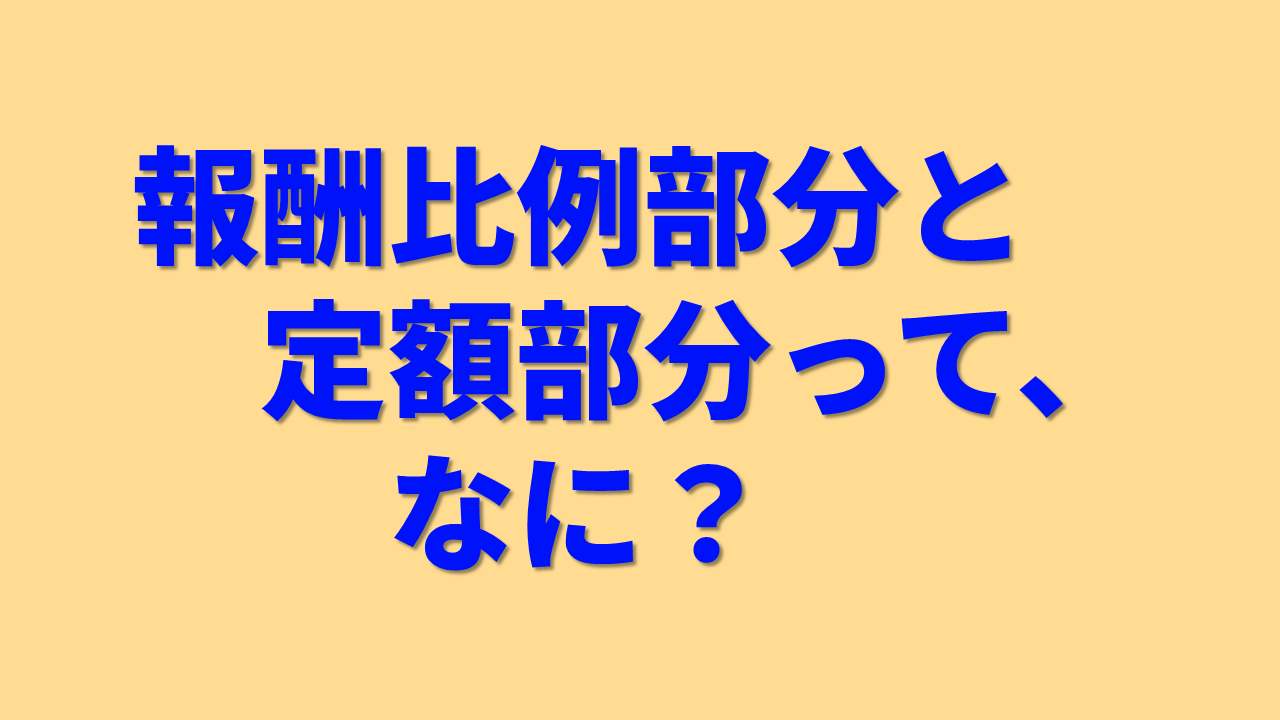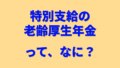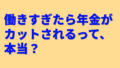この前の話で、65歳になる前からもらえる、特別支給の老齢厚生年金というのがあるということはわかったよ。
でもねんきん定期便にはその内訳として、「報酬比例部分」と「定額部分」というのがあるけど、これは何だろう?

さっぱりわからん。
年金や制度って、なんだろう?
子どもに聞かれて、うまく答えられなかった。
その経験を出発点に、このブログでは、社会保障のしくみを、ひとつずつ、いっしょに見ていきたいと思います。
前の記事では、特別支給の老齢厚生年金とは何なのかということについてお話しましたね。
ここでは、更にその内訳について、みていきましょう。
「報酬比例部分」と「定額部分」って何?
ねんきん定期便に出てくるふたつの言葉
「65歳になる前から年金がもらえるらしい」と聞いて、ねんきん定期便を見てみると、「報酬比例部分」「定額部分」という言葉が並んでいる。
でも、これって何だろう?と感じたことはありませんか?
このふたつは、特別支給の老齢厚生年金の中にある支給のかたちなんですね。
「報酬比例部分」は、働いていたときの給与に応じて年金額が決まり、
「定額部分」は、報酬に関係なく、加入期間に応じて一定額が支給されます。
それぞれ別の仕組みとして語られますが、もともとは厚生年金の中でひとつの年金として組み合わされていたものなのです。
昭和29年、定額部分が加わった
報酬比例だけでは足りない
昭和29(1954)年の制度改正以前、厚生年金は報酬に応じた部分だけで構成されていました。
でもそれでは、報酬が少なかった人の年金額も少なくなってしまい、生活の支えとしては不十分だという声があったんです。
加入期間に応じた支えとして
そこで、報酬に関係なく、加入期間に応じて支給される定額部分が加えられました。
この改正によって、厚生年金は“報酬に応じた部分”と“期間に応じた部分”の両方を持つようになり、より多くの人の暮らしに寄り添う制度へと整えられていったのです。
昭和36年、国民年金制度の創設
厚生年金加入者と国民年金の関係
昭和36(1961)年に国民年金制度が創設され、すべての人が年金制度に加入する仕組みが始まりました。
厚生年金に加入していた人は、あらためて国民年金に加入したわけではありません。
すでに持っていた定額的な支給の仕組みが、国民年金制度の中で果たす役割と重なるように整理されました。
拠出による支え合いの仕組み
このときから、厚生年金加入者の保険料の一部は、国民年金の財源として拠出されるようになり、制度の中で支え合う仕組みが広がっていったのです。
今は「定額部分」は支給分のみ
現在の厚生年金では「定額部分」という言葉は使われていません。
また、定額部分のための保険料を納める仕組みも、今は存在していません。
けれど、かつての制度の中で厚生年金に加入していた人の中には、報酬比例部分と定額部分の両方を受け取っている方もいます。
それが、特別支給の老齢厚生年金です。
この特別支給は、昭和36年4月1日以前に生まれた方など、一定の条件を満たす人に限って、65歳前から支給される仕組みです。
報酬比例部分と定額部分は、それぞれ支給開始年齢が異なり、生年月日によって段階的に引き上げられてきました。
こちらについてはいつかまた別の記事で書いてみようと思います。
詳しくは、以下の公式サイトもおすすめです。

何か難しかったけど、つまり、もともとは厚生年金があって、それが二つに分かれた。
ある年齢より上の人は、その二つを、別々に、早めに受け取れるっていうことだね。
それと、二つにわかれた一つは国民年金みたいなものに変化した、と。
ややこし~。でもなんとなくだけどわかった…ような、気がする。