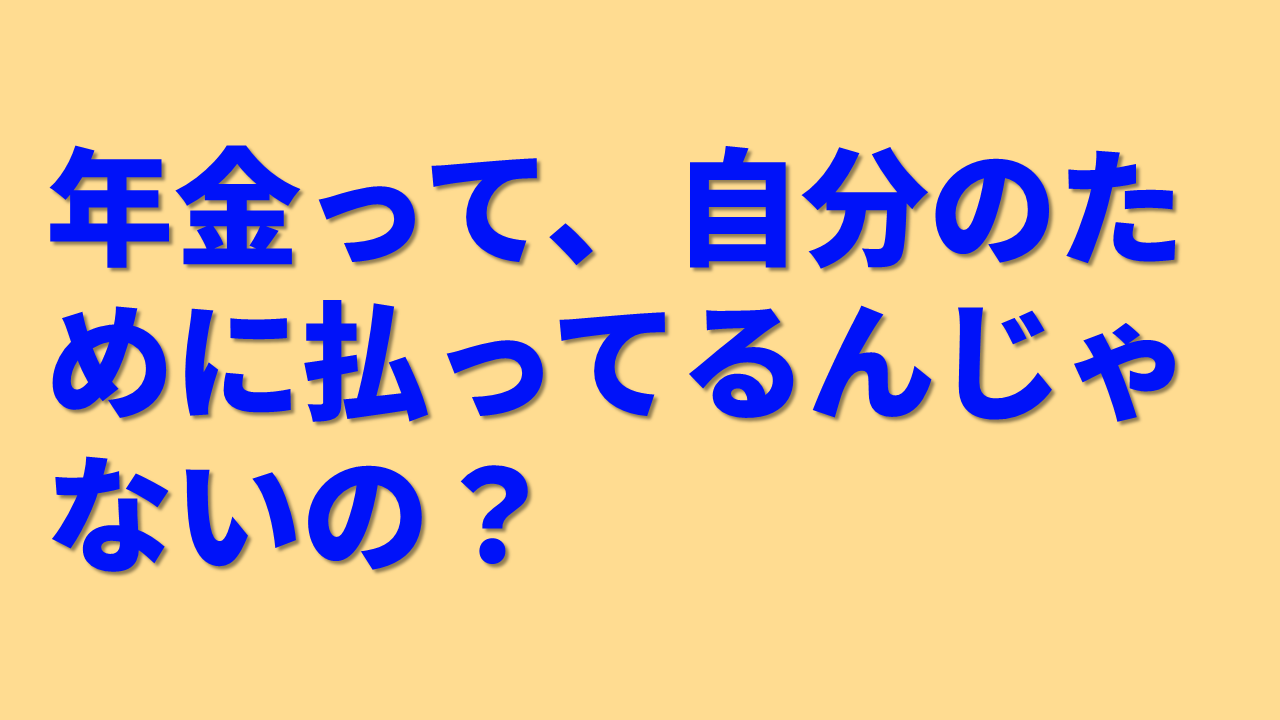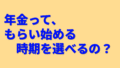ねえ、父さん。
ネットで“高齢者を1人で何人が支える肩車社会”って見たんだけど、どういうこと?
年金って、自分が払った分を、将来自分で受け取るんじゃないの?

若い世代の負担が…っていう、あの話のことだよね。
年金って、なんだろう?
子どもに聞かれて、うまく答えられなかった。
このシリーズでは、そんな問いの入り口を、ひとつずつ一緒に見ていきましょう。
今払っているお金は、誰のため?
今の保険料は、今の年金になる
日本の年金制度は、「今働いている人が払うお金」が「今の高齢者の年金」として使われる仕組みになっています。
このしくみのことを、専門的には「賦課方式(ふかほうしき)」と呼びます。
つまり、毎月払っている保険料は「自分のために貯めている」わけではなくて「今の高齢者の生活を支える」ために使われているんです。
じゃあ、自分の分はどうなるの?
世代をつなぐリレーのようなしくみ
この制度は、世代を超えて支え合う「リレー」のようなものです。
- 今のあなたが払う → 今の高齢者が受け取る
- 将来あなたが高齢者になる → そのときの若者が支える
年金は「貯金」ではなく、「仕送り」に近いしくみです。
自分の口座に積み立てているわけではなく、社会全体で支え合う制度なんですね。
いつからこのしくみが始まったの?
みんなで支える制度が必要だった時代
このしくみが整えられたのは、戦後まもなくの1950年代。
当時は、老後の生活を家族が支えるのが当たり前でした。
でも、家族だけでは支えきれない人も増えてきて「社会全体で支える制度が必要だ」という考えから、年金制度が整えられていきました。
そして1961年には、すべての人が何らかの年金制度に入る「国民皆年金」が始まりました。
年金って、老後だけの話じゃないの?
もしものときにも備えるしくみ
年金は、老後の生活費だけじゃなくて、 もしものときの「保険」としても役割があります。
たとえば——
- 病気やけがで働けなくなったとき → 障害年金
- 家族を残して亡くなったとき → 遺族年金
こうした給付も、みんなで支え合うしくみの中に含まれています。
この制度は、これからも続くの?
今の支えが、未来の支えにつながる
今あなたが払っている保険料は、今の高齢者の生活を支えています。 そして、将来あなたが高齢者になったときには、次の世代があなたを支える。
そんな「つながり」が、年金制度の根っこにある考え方です。
別記事では年金制度は崩壊しないの?ということについて書いています。
もっと詳しく知りたいときは?
制度のしくみや最新の情報は、公式サイトで確認できます。
[参考]
厚生労働省「賦課方式と積立方式」